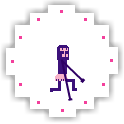※なんとか無事に終了しました
CETとは「セントラル・イースト東京」のことです。今年で6年目、もう始まってます。これまで展示やトークイベント、人生相談などに参加してきました。東京の東側エリア、日本橋、浅草橋を中心に点在する空きビルを期間限定で貸してもらって、展示やイベントを開催するというオルタナティブな催しです。東東京の町おこしみたいなものと思ってください。とはいえこの活動の中からは「東京R不動産」のようなユニークなプロジェクトも生まれてる訳ですから侮れません。そして今回はあのピエール・バルーがフリーマーケットに出品するという、にわかには信じがたい事態となっています。
さて今年に入って絵画部というのをはじめました。絵について話し合うのが主な活動ですが、それが高じて美学校で講座を持つこととなり、このたび部員一同集まって公開制作をする運びとなりました。金融危機を憂うスタイリストツヨポンによって仕掛けられた黒人コスチューム&トン子ちゃんを、定められた日程で描ききらなければならないという条件の上、各々日々の仕事があるのため合間を縫って作業しなければならず、いつ描きに行けるか分からないという大変不安なミッションです。せっかく見に行ったのに誰もいなかったとの苦情がさっそく出ておりまして、こうして告知していながら心苦しい次第です。
10日が中間講評、12日に展示&講評会をおこなう予定なので、この両日の活動時間18:00〜22:00は部員全員そろっているはずです。よろしければそのタイミングでお立ち寄りください。なお部室まではとても迷いやすい道のりとなっています。私は三度迷いました。念のため地図を二種類リンクします。
部員:佐藤直樹×マジック・コバヤシ×池田晶紀×小田島等×都築潤
場所:東京都中央区日本橋大伝馬町15-3内田ビル地下 地図1/地図2
※巡回展も含め終了しました
12月5日からペーターズギャラリーで「ことしの仕事展」が始まります。各々のイラストレーターが今年の仕事をひとつピックアップして、その原画といっしょに媒体を展示するという企画です。媒体とはいわゆるマスメディアの複製物のことで、ポスターだったり雑誌の紙面だったり、ピックアップされた仕事によってさまざまな種類が展示されるものと思われます。そしてイラストレーションとは原画ではなくこの複製物の方だというのが私の考えです。
イラストレーションつまり「図版」として使われる絵の供給者であるイラストレーターの職能は、その媒体に対してビジュアルをアジャストさせるアイデアや技術だと考えられます。しかしその仕事の性質が、アドバタイジングのアートディレクターシステムのように分業的要素が強ければ強いほど、アイデアの主要部分であるデザイン計画のほとんどがクリエイティブディレクターやアートディレクターに委ねられることになります。もちろんイラストレーターがアートディレクターを兼ねていれば話は別ですが。
逆にその要素が弱いのが出版の挿絵やカットの仕事かと思います。結果的にどちらの世界が合うかはイラストレーターの性格によって違うでしょうし、そのイラストレーターが志向する絵や仕事のスタイルによっても違います。もちろん人間関係の違いがそれを決定づけることも珍しくありません。そして現在はとてもじゃないですが「どちらの世界」で割切れるほど、イラストレーターという職業の幅は狭くないのです。
このような仕事上の経験を経て、知らず知らずのうちにイラストレーター各々の中にハビトゥスが形成され、志向の近いもの同士がグループ化します。「イラストレーター」という職業についての認識も他のグループとは違うものになっていきます。それにともない社会からの認知や要請も多様化し、同じ肩書きでもまったく違うビジネススタイルになっていくというわけです。しいて共通点をあげれば「絵を描いている」ということぐらいでしょうか。こうした傾向はなにもこの世界に限ったことではありませんよね。
かくしてイラストレーターの意味は広がりました。最低限絵を描いていれば誰でもそう名乗る自由があります。さてこの展覧会のメンバーを見渡しますと、「イラストレーター」の前提にそれほど認識の違いはなさそうです。あるとすれば「イラストレーション」の方かな。こちらに対する考え方の違いはけっこうありそうなので、それを念頭に置いて観ていただけると面白いんじゃないでしょうか。以上「イラストレーターの仕事シリーズ」という副題があったので、そのことについて偉そうに書いてみました。
会期:2008年12月5日(金)~12月24日(水)
会場:ペーターズギャラリー 地図
サイトを徐々にリニューアルします■■■
TOPページに REPORT をもってきました。
ARCHIVEへのリンクを新たに加えました。(081116)
ARCHIVEのリンクをバナーにしました。(081120)
PROFILEにプロフィール詳細をアップしました。(081126)
TOPぺーじに関連書籍の紹介を開始しました。(090128)
ARCHIVEに Guide in campus を追加しました。(090316)
Aboutを修正、加筆しました。(090317)
ARCHIVEに Cyzo feature を追加しました。(090517)
TOPページに REPORT をもってきました。
ARCHIVEへのリンクを新たに加えました。(081116)
ARCHIVEのリンクをバナーにしました。(081120)
PROFILEにプロフィール詳細をアップしました。(081126)
TOPぺーじに関連書籍の紹介を開始しました。(090128)
ARCHIVEに Guide in campus を追加しました。(090316)
Aboutを修正、加筆しました。(090317)
ARCHIVEに Cyzo feature を追加しました。(090517)
※おかげさまで無事終了しました
8月20日に中ザワヒデキ氏と対談があります。場所は神保町の美學校、入って左側の教室だそうです。あらかじめ断っておきますが冷房がありません。そんな事情もあって入場無料です。
これまでの中ザワ氏とのトークでは概ね「絵画」を議論してきました。でも三度めの今回は美學校でやるにもかかわらず「イラストレーション」がテーマです。こんな話ができるのも、氏が90年代初頭イラストレーターだったからというだけでなく、欧米のアートのとある動向が、日本のデザイン方面に捻れて現象した一時期があったことを、日本美術の系譜に積極的に取り入れ発言している作家だからです。そしてこのことが、中ザワヒデキという美術家をたいへんユニークな存在にしてる原因のひとつでもあります。
輸入当時のイラストレーションという言葉は状況や機能を指す名であり、絵に内在する性質や特徴と関係ありませんでした。少なくとも50年代は写真もイラストレーションと呼ばれていました。簡単に言っちゃうと、印刷された(つまりグラフィックデザインであり複製媒体の)文字以外のビジュアル部分をイラストレーションと呼んだだけです。イラストレーションとは「コピー」とか「キャプション」とかと同じ広告デザインの用語だったんです。
このようなイラストレーションという言葉の使用法は、音楽でいえば「BGM」といっしょです。ベートーベンだろうが湘南乃風だろうがただの口笛だろうが、複製してBGMとして使えばBGMだし、そうじゃなければBGMではありません。モーツァルトが新曲を書き上げた瞬間「いいBGMができたぞ」とは言いません。同じようにイラストレーションとして使えば(つまり印刷されれば)どんな絵もイラストレーションです。
さて日本ではイラストレーションが「イラストレーターが描いた作品」という意味にまず転倒します。その後は「イラスト」と略称されるとともに、独特の発達というか変化をとげてゆくのですが、それがなだれ込むようにピークに達したのが70年代で、「アート」という言葉で息をつないだのが80年代ではないかと考えられます。グラフィックデザインとアートが表向きお互いを包摂し合う奇妙な現象で、この出来事をわりあいベタに受け止めた人たちの中には、今でも「イラスト」にいい印象を持ってない人がけっこういるようです。もともと美術方面では、イラストレーションを「浅はかな具象画」といった意味で蔑称として使ってきたこともあり、何となく評判の悪い言葉になっています。もっともそういう意味でないことは上記したばかりですが。
その他いろいろあって、アートをデザインやイラストレーションと絡めて論じる時は、その定義について説明することに気を使います。未だに「アート」「デザイン」「イラストレーション」の前提を各々が共有してないせいで、この手の議論が不毛に終わることがとても多いからです。「機能はイラストレーションに従う」と82年当時言ったのは美術評論家の中原佑介でした。言外の意味も含め、こうした前提があってはじめてセンセーショナルに響く言葉だと思います。
日時:2008年8月20日(水)19:00〜
会場:美學校
入場無料 予約不要
※中ザワヒデキ:プロフィール/著書/寄稿
※おかげさまで無事終了しました
このカバーイラストレーションはカズモトトモミさんです。そのカズモトさんとの対談が5月23日にあります。カズモトさんは一応イラストレーターですが、おそらくイラストレーターという肩書きに疑問を持っているタイプのイラストレーターではないかと思います。こう言うと、じゃあイラストレーターじゃなくてアーティストって呼ばれたいの?という意味で捉えられがちですが、事態はそう単純ではありません。
で、そういう内向きの話はおまけで触れることにして、今回の対談は「媒体と作風」についての話題がメインになると思います。カズモトさんに対しそういう興味が湧くのも、この人が、漫画みたいな絵、シリアスなシルクの作品、図解、その他「絵」を目的別に描き分けること、そしてそれぞれを高いレベルで処理(ここポイントです)することに、強い執着を持っている作り手の一人だとお見受けするからです。目的のためなら作風は捨てて良しと言わんばかりの気迫です。さて、それがグラフィックデザインとしての「機能」を考えてのことなのか、アートでいうところの「シミュレーショニズム」の援用なのか、そうした手法にどんな利点とリスクがあるのか、まずはその辺からお尋ねしたいと考えています。
※茶ノ間:ワークショップ内容/問い合わせ&Map
※カズモトトモミ:プロフィール
カレンダー
| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最新記事
(06/08)
(06/08)
(08/31)
(10/21)
(09/03)
カテゴリー
関連グッズ
ブログ内検索